機能要望アンケート変更
POPFile 日本語化機能要望アンケート
http://popfile.sourceforge.jp/cgi-bin/enq.cgi
を少し変更し、一人一票の制限の有効期間を1週間にした。つまり1週間すれば、また新たに投票できる。
http://sourceforge.jp/forum/forum.php?thread_id=5157&forum_id=3073
2004/05/11 09:00:00
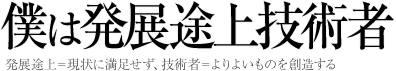
POPFile 日本語化機能要望アンケート
http://popfile.sourceforge.jp/cgi-bin/enq.cgi
を少し変更し、一人一票の制限の有効期間を1週間にした。つまり1週間すれば、また新たに投票できる。
http://sourceforge.jp/forum/forum.php?thread_id=5157&forum_id=3073
2004/05/11 09:00:00
久々に POPFile をいじってみた。insert.pl を日本語対応にした。パッチを
http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=952353&group_id=63137&atid=502958
に投稿。
メールを1行ずつ読み取ってデコードおよび分かち書きをするという方針に変更したおかげで、insert.pl の変更は非常にすっきりしたものとなった。
2004/05/11 09:00:00
著者の野口悠紀雄は大学教授というえらい地位にあり、そして年齢は60を越えているにも関わらず、まだ英語を、そして新しいことを勉強しようというその姿勢にはおそれいる。僕が尊敬する人のうちの一人だ。
英語を聴く能力がものすごく重要だということを非常に明確な論理で説いている。会話の中で、ネイティブの言った言葉を聴きとり、それをおうむ返しで使うことによって会話を成立させるテクニックには「なるほど」と感じた。
他の英語勉強方法については、よく考えれば自分がおこなってきたことと同じなのだけれど、「この方法で良かったんだ」と再確認させてくれることにより、同じ勉強方法もより効率が良くなる。「この方法で正しいんだろうか」というもやもや感をサッと取り去ってくれた。
その再確認された点をいくつか挙げると、
英語は丸暗記法で勉強せよ
高校のときに、駿台予備校が出版する「英文700選」という重要例文が並んだ参考書を使い、友達と10個ずつ覚えてはそらんじて書き出すテストをした。そして、間違いが少ない方が100円もらえる、というようにしたのだ。この「人と競う」という要素を入れると何か目標を達成したいというときに有効だと思う。TOEIC や TOEFL といったテストを目標に勉強するというのも、この「競う」要素の一種だろう。
英語の勉強は楽しい
単語帳や重要単語を並べただけの参考書はこの本では否定されているけれども、僕は基礎作りとしては避けて通れない道だと思っている。例文を覚えるという作業と合わせてこの部分は一種の修行だ。スポーツの筋トレのようなもの。その後は英文がわかるようになり楽しくなってくる。知らない世界が開ける感じだ。まだ日本語訳されていない洋書を読む、あるいは日本でまだ公開されていない映画を観る、というのがそういった楽しみの一部である。
会話ではネイティブの相手が言ったことを利用する
あるときから会話がとたんに簡単になった僕のテクニック。まず、「もう一度言って下さい」「ゆっくり言って下さい」というフレーズを覚える。教科書には I beg your pardon? とか Could you speak more slowly? なんて書いてあるが、ネイティブが聴き返すときに Sorry? としか言っていないのを聴いて以後は、聴き返すときは Sorry? 、それでも分からないときは、In other words?
とか More slowly, please? とだけ。それで充分通じる。
また、相手が言ったことの一部だけわからなかったときには、その部分を名詞でも動詞でも何でも単に What に置き換え、あとはおうむ返しに、そして語尾を上げて聞く。例えば I have a pen の pen が聞き取れなかったとしたら、「持っている”もの”が聞き取れなかったのだから What で聞いて、you だから does じゃなくて do を使うんだろう」というように頭の中で英文法を一生懸命思い出し、疑問文を構築して、 What do you have? と聞くよりも You have what? と聞く方がよっぽど簡単だ。
英語力と言ってもいろいろな種類がある
http://d.hatena.ne.jp/jishiha/20030523#p1
でも書いたことだけれど、英語力には「仕事のための英語力」とか「原書を読むための英語力」、「映画を字幕なしで理解するための英語力」のようにいろいろな種類があり、それぞれ勉強方法が違う。どれが自分が必要としている英語力なのかを見極めて、それにあった勉強方法を取らなければならない。アメリカ生活は5年目だが、やっぱりいまだに映画を字幕なしで理解できないけれどもう落ち込むことはない。(と言いたいところだが、やっぱり少し落ち込む)
2004/05/06 09:00:00
間違い電話がかかってきた。それも2度続けて。以下のような対応例が考えられる。
対応例その1「だから、おまえのかけた番号は間違いだ、って言ってんだろ。バカ。」(切)
対応例その2「電話取った瞬間、まだプッシュ音が聴こえていたよ。たぶん番号押している途中で僕の番号にかかっちゃったんじゃないかな。エリアコード番号が間違っているんじゃない?」
僕は対応例その2で実際に対応したのだけれど、対応例その1のような対応をする人って驚くほど多い。「2ちゃんねる」とかで。
ちなみに「間違い電話だよ」と英語で言う時は、Wrong number だ。I think you dialed wrong number. などと言う。
2004/04/30 09:00:00
暗唱番号やパスワードは不要:電話上の声紋で本人確認
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20040430105.html
(http://d.hatena.ne.jp/masah/20040430#p12 より)
すごく画期的だと思う。こういう画期的な製品は実際に試して、その実力のほど、つまり本当に声紋を認識するのかどうかを確かめてみたくなるものだ。
簡単なデモンストレーション、例えば用意されたフリーダイアルに電話して、自分の声を吹き込み、次にもう一度認証用に別のフレーズをしゃべって認識できるかどうかが試せるなんていうのが用意されているといいのに。試しに他の人に認証用にしゃべってもらったら、ちゃんと「別人です」と認識する、という具合に。そうしたら、きっと何倍もの感動を与えることができると思うのだが、残念ながらそのようなデモは用意されていない。おしい。
以前、http://d.hatena.ne.jp/jishiha/20040122#p1 で紹介した海外で日本のテレビ番組が観られるサービス 6ga.net には非常に優れた「無料お試し」システムが用意されている。このサービスはリモートのテレビパソコンで録画した番組を観ることができるというサービスだから、別に海外にいる必要はない。ただ日本にいたら、日本の番組はテレビから直接観られるのでそのありがたみは海外在住の日本人に特に大きいというだけ。だから日本にいる人でも「無料お試し」は気軽にできる。「感動を与えるデモンストレーション」を実感できると思う。
2004/04/30 09:00:00
http://www.nobel.se/peace/educational/conflictmap/index.html
(http://d.hatena.ne.jp/masah/20040428#p9 より)
伝えている内容は深刻だが、ユーザーインターフェースの素晴らしさに目をみはった。時間とともに変化する空間上の出来事をうまく表現している。うまく説明できていないので、百聞は一見に如かず、Conflict Map(直リンク)を表示し、年代を表すスライドバーの右端をドラッグして、現在つまり 2000 の少し右まで動かしてみて欲しい。この100年間にどこでどれだけ紛争・戦争が起こったかが一目瞭然だ。
2004/04/28 09:00:00
評価:9/10
「映画」にカテゴリ分けしたが、「24」は映画ではなくテレビドラマだ。しかしその面白さは映画以上。
日本でも大人気らしく、何をいまさらという感じなのだが、日本にいる弟から、「これは絶対見るべき、面白い」と薦められ、近くのレンタルビデオ屋から借りてきて観た。暴力シーンがあるものは子供が起きている間は見ないようにしているので、朝子供が起きてくる前に観るようにしたのだが、常に次のエピソードを観るのが楽しみだったおかげで6時前起床がほとんど苦にならずに実行できた。
24時間の出来事をリアルタイムで24話に収めるという画期的な試みはおおかた成功しているが、やはり話に無理がある部分がいくつか目についてしまう。あっと思わせる裏切りがいくつかあるのだが、「あれ、何でこの人もっと最初から裏切っていなかったのだろう」と思ってしまう。それが1点減点の理由。
せっかくアメリカにいるのに、リアルタイムで観られなかったことが残念でしかたがない。そういえば、イチローが初めてオールスターに出場したときに、そのときの放送でしきりに「24」が宣伝されていたことを思い出す。そのときに観ていたら、日本の誰よりも早くこの面白さを知るという優越感にひたれたのに。ちなみに現在はシーズン3が放送中だ。
2004/04/27 09:00:00
在サンフランシスコイーストベイエリアの日本人および日系アメリカ人が主体となったゴルフトーナメントに毎月参加している。結果が良くて気分が良いので書くのだが、スコアは 52-49-101 だった。ここのところずっと不調だったのだが、久しぶりにハーフで50を切ることができた。
早起きしてずっと練習していたパットだが、今回もうまくいかず、それでだいぶスコアを落としている。家で決められた距離だけをマット上でおこなう練習を見直す必要がある。
ゴルフは難しい。僕なら100近いショットを、いかに練習通り打てるかどうかにかかっている。うまく打つためのチェックポイントというのが僕には3つほどあるのだが、これを毎回毎回きちんと守れるかどうかが勝負だ。ゴルフの敵は他人ではなく自分、などと言われるがまさにその通り。やろうと決めたことを実行できるかどうかなのだ。
僕は大学のときにアーチェリーをやっていたのだが、決められた動作を繰り返すという意味でゴルフと似ている。アーチェリーでスコアが良いことを俗に「あたる」と言っていたのだが、「あてるためには決められた時間にパッと起きる」という一見意味のないように思える教えを受けた。しかし、これが実は結構重要。いままた、ゴルフでもこの重要性を再認識している。この一ヶ月、「6時前に起きる」という目標を立て、おおかた実行できているのだが、まだ寝たいという欲望を振り切りベッドから起き上がるときの精神状態は、くずれそうになるのを我慢してゴルフのショットをするときの精神状態に似ている。
やろうと決めたことを実行する習慣を持つことがゴルフがうまくなるための秘訣だと思う。「ゴルフがうまくなりたければ早起きをする」は少なくとも僕にとっては効くように思える。
2004/04/26 09:00:00
1920年にできたといった旧い電車に実際に乗ることができる。Restoration されていて実際に走るのだ。鉄道マニアにはきっとたまらないのだろう。鉄道マニアになりかけのもうすぐ3歳の息子も大喜びだ。
このような施設ではチケットを買ったら普通は一回しか乗れないものだが、ここのチケットはその日のうちだったら何回でも乗れてしまうところがうれしい。
2004/04/24 09:00:00
株式会社まちクエスト代表、つくる社LLC代表。
Scratchで楽しく学ぶ アート&サイエンス、Raspberry Piではじめる どきどきプログラミングを書きました。
オンラインコンテンツ: 大人のためのScratch
Amazonから図書館検索 Libron、iPhoneアプリ ひらがなゲーム かなぶん を作っています。
Email: webmaster at champierre dot com
Twitter @jishiha
@jishiha をフォローする